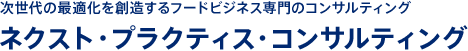現場のファクトファインディングが飲食店の腕の見せ所
前々回、短絡的な「リストラ」で「知的資本」が流失してしまう危険性を述べました。
「知的資本」が流失することなく、「リストラ」を進めていくには、そのアクションの優先順位付けと、リソースの配分が大切になってきます。
具体的には、
① 自社の各部門がどのような「ステータス(立場)」に置かれているか
② 各部門のバリューチェーン(会社の価値連鎖)にかかわるステークホルダー(利害関係者)が、どのように評価され、何を期待しているか
を十分に精査しなければなりません。
すなわち、まずは「現状」の把握で、一般的には「ファクトファインディング」と呼ばれます。
事前に各部門の「実態調査」をしっかり行っておけば、「リストラ」後の一時的な厳しい局面を迎えても、何に注力し、何を推進しなければならないかは、「構造的」に把握できるはずです。
また、「リストラ」の目的として「選択と集中」を掲げる会社が多い中、「ファクトファインディング」がしっかりできていなければ、スムーズに事は運びません。
すなわと、「選択と集中」とは、「企業戦略」の優先順位付けに他ならないからです。

このビジネスにおける考え方を、飲食店に置き換えてみると、
飲食店において、「顧客の事実を掴む」=「実態調査」とは、何気ないお客様の会話(話)に聞き耳を立て、お客様の事実を掴むことです。
顧客の声(事実)から何を選択し何に集中するか。
そう考えれば、仮説も立てられ、その先にある課題解決にもつながります。
「顧客の事実を掴む」、ファクトを掴むということが飲食店における「ファクトファインディング」です。
お客様はある例外を除き、自ら進んで要望を口に出すことはありません。
お客様の口にしない(隠された)、真の要望(課題)を見つけ出し、改善することが店長(店主)の腕の見せ所です。
そして、ある例外もあるので、一過性の要望ではなく、定量的に発生しているデータが大切です。
例えば、お客様のご意見を記帳していくと、そのデータから個々のご意見から、ある関連付けができます。
その関連付けされたものを、従業員全員と共有すると、「そういうことか」と合意形成(アグリー)ができ、そこから急速に改善・提案が進みます。
飲食店における「ファクトファインディング」と、顧客の視点だけではなく、従業員の視点も含め、現場の「実態調査」から始まります。
中小規模のフードビジネスにおける、エリアマネジャーやスーパーバイザーなどが単に臨店することとは意味合いが大きく違います。
【関連記事】
【前回記事】
※「共創戦略研究所」とは、NPCが福岡市で運営するプロジェクト支援事業で、NPCとはネクスト・プラクティス・コンサルティングの略です。